こんにちは、ささぶねです。
今回のテーマは「言葉と心の裏読みはエネルギーバンパイア(吸血鬼)!」です!
それではどうぞ!
目次
いつも「忖度(そんたく)」している国、日本
2017年に「忖度(そんたく)する」という言葉が話題になり、この年の流行語大賞になりました。
「忖度する」とは
人の気持ちを考える、人の気持ちを察する、人の気持ちを思いやる、人の身になって考える、相手の身になって考える、おもんぱかる、推し量る、推量する、空気を読む
と辞書にあります。
つまり「忖度する」とは「相手を思いやること」を言うんですね。
「空気を読む」という意味で使われている場面も多いと思います。
ここ日本では意識せずとも普段から「忖度」して「空気を読んでいる」人は多いと思います。
いまこれを読んでいるあなたも今まで、仕事、学校、チームスポーツなどの場などで「集団における和を尊ぶように!」と教育される機会がたくさんあったのではないでしょうか。
日本人は幼少の頃から生活のあらゆる場面において、「言葉の行間を読み」「言葉の裏を読み」「場の空気を読む」ように訓練されてきました。
だから「忖度する」ことが得意で、もはや無意識レベルでそれを行える人がたくさんいますね。
「忖度する」ことは「相手を思いやること」なので大変素晴らしいことです。
ですが相手のことを思い過ぎるあまり、自分が思っていることをそのまま伝えられなかったり率直に意見を言えなかったり・・・
なにか「息苦しさ」のようなものを感じてしまう・・・
そういった経験をしてきたという人も多いのでは無いでしょうか?
相手の言葉の裏を読むことは膨大なエネルギーが浪費されてしまう
ここで私個人の話になるのですが、ささぶねは学生の頃にアメリカの田舎に留学していたことがあります。
言葉が分からず困ったーーーー!
そんな経験ももちろんあるのですが、
アメリカの地に暮らして「ああ、これは心地いいなぁ・・・」と初めて感じたことがあったのです。
それは「相手が発する言葉はその言葉通りに受け取って大丈夫」という体験でした。
「相手はこのように言っているけど・・・でも本音は別にあるんじゃないか?」
会話中、相手の言葉と心の裏読みをすることにすっかり慣れてしまっていた私にとって、「相手の言葉の裏や隠れた意図を推測しなくて良い」ということは最初はなかなか信じがたいことでした。
ですが「言葉と心の裏読みをしない会話」に慣れていくほどに、気がついたことがあったんです。
会話をしてもぜんぜん「気疲れしない」こと。
相手の言葉を「安心して」そのまま受け取れること。
自分の「思うことを思ったとおりに表現」しても誰も困らないこと。
相手の言葉をそのまま受け取り、自分も本音で話せる会話は「相手との信頼感がより高まる」こと。
そして日本にいる時の自分の会話を振り返り、このようも思いました。
「ああ・・・言葉と心の裏読みをする会話に、今まで自分はこんなにも多くのエネルギーを浪費してきたのか・・・。」
「言葉と心の裏読みをする会話」は自分が思っている以上に「心理的エネルギー」をものすごく沢山消耗していた。
そのことに気付かされたのです。
あまりにも当たり前に身に付いてしまっていたこと、普段から無意識で行っていることは、一度完全にそれをやめてみないとなかなか気が付かないものなんですよね。
ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化の違い
「言葉」の成り立ちには歴史的、文化的な背景がその土台にあります。
アメリカと日本ではそもそも「言葉が持つ文化」が違うのです。
アメリカは「ローコンテクスト(Low Context)文化」です。
対して日本は「ハイコンテクスト(High Context)文化」であるという違いがあります。
「コンテクスト」とは文脈・筋道・背景という意味です。
アメリカは移民も多く多民族国家で、様々なバックグラウンドを持つ人びとが暮らしています。
そのような環境下では「あえて言わなくても誰もが分かるでしょう?」という共通概念をお互いが共有するのは難しいことです。
だから「ローコンテクスト文化」では「具体的に、明示的に、シンプルにわかりやすく伝える」ことがとても重視されます。
一方で、日本は島国であり、ほぼ単一民族で国が成り立ってきた歴史があります。
日本ではお互いに共有している知識や経験などの共通概念があることを前提とした会話をします。
「あえて細かいことを言わなくても相手は分かってくれるはず!と思い多くを話さない」、「空気を読む」、「相手が察することを期待し曖昧な表現をする」といった会話が「ハイコンテクスト文化」ではなされるのです。
| ローコンテクスト文化 |
|
| ドイツ系スイス人、ドイツ人、スカンジナビア人、アメリカ人、フランス人、イギリス人 |
| ハイコンテクスト文化 |
|
| イタリア人、スペイン人、ギリシャ人、アラブ人、中国人、日本人 |
英語と日本語の違いというのは使用する文字や文法の違いだけではなく、文化的な考え方の違いが大きいんです。
私がアメリカに住んでみてわかったこと。それは・・・
お互いに空気を読み合うハイコンテクストの会話をするのは思っていた以上に「気疲れしていた」ということ。
そして会話の相手にも「気疲れさせていた」こと。
「会話の時に今までずっと余計なエネルギーを使ってたんだな・・・」ということをローコンテクスト文化に浸かってみて初めて実感しました。
「空気を読み過ぎる」「忖度し過ぎる」・・・・
言葉と心の裏読みは自分にとっても相手にとってもエネルギーバンパイアだった!ということがこの時に身にしみて分かったんです。
そして「相手の会話や心の裏を読まない」「相手の会話をそのままの意味で受け取って良い」ことのあまりの楽チンさに感動を覚えました。
言葉に裏が無いことは相手のエネルギーを奪うことが無く自分も消耗しない
私の友人に「相手の言葉の意図や目的、会話の着地点を読む」のがめちゃくちゃうまい人がいるんです。
将棋でいうと5手先~10手先くらいを常に読みながら会話ができる人です。
その子と会話すると、頭のCPUの性能の高さを感じて「うわ、すごいなぁ・・・!」といつも感心してしまいます。
とても親切で優しい友人なので、いつも私を思いやって会話を進めてくれるのは本当にありがたいのですが、
「会話するのに疲れないかなぁ・・・?」「大丈夫かなぁ・・・?」とたまに心配になってしまうということをその友人に伝えました。
私はその時自分が思っていることを出来る限りそのまま相手に伝えるようにしています。
もちろん何でもかんでも言って良いと考えているわけでは無いのですが、
自分が「言葉に裏を持たせないで会話する」ことによって、相手が「その言葉通りに受け取って良いんだ」と安心してもらえたら嬉しいからです。
「空気を読まない」「忖度しすぎない」ことで心理的なエネルギーを温存できれば、お互いに「気疲れしない」「エネルギーを無駄に浪費しない」で済むと考えています。
会話をエネルギーバンパイア(吸血鬼)にしない為に
- 「空気を読むこと」を極力やらない
- 自分が考えていることや感じていることを出来るだけ素直に相手に伝える
と私は決めています。
まとめ
今回は「言葉と心の裏読みはエネルギーバンパイア!」ということについて書きました。
いかがでしたでしょうか?
「空気を読む」「忖度する」ことは相手を思いやることの一つの形です。
日本人にとってはとても得意なことで素晴らしい長所のひとつだと思います。
でもそれも度が過ぎてしまうと
「なかなか自分の本音を言えない」「いつも遠慮してしまう」「息苦しさを感じる」・・・
日本においてはそんな会話をお互いにやってしまいがちです。
「空気を読む」のも「忖度する」のもやりすぎは禁物!!
「相手の言葉と心の裏読みをしない」「あえて空気を読まないで率直に意見を伝える」ことで会話に安心感と信頼感をもたらす。
そしてお互いに心理的エネルギーを消耗しない!
そういう利点もあるよね!というお話でした。
会話ってほんとーーにムズカシーーーーーー!!
でも・・・・いろいろ試行錯誤できるから面白いですよね!
今回はこれにて!
ささぶねでした!
ささぶねの詳しいプロフィールはこちら!⇒ プロフィールを見る
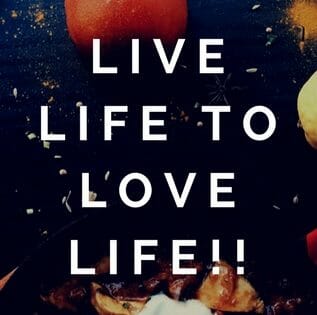

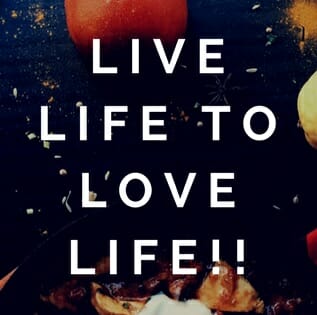
コメント