こんにちは、ささぶねです。
今回は「近江商人の商売の極意『商売の十教訓』」についてご紹介します!
目次
- 商売の心得「三方よし」で有名な近江商人とは?
- 近江商人の経営哲学「商売の十教訓」とは?
- 一、商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり
- 二、店の大小よりも場所の良否、場所の良否よりも品の如何
- 三、売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永遠の客をつくる
- 四、資金の少なきを憂うなかれ、信用の足らざるを憂うべし
- 五、無理に売るな、客の好むものも売るな、客の為になるものを売れ
- 六、良きものを売るは善なり、良き品を広告して多く売ることはさらに善なり
- 七、紙一枚でも景品はお客を喜ばせる、つけてあげるもののないとき笑顔を景品にせよ
- 八、正札を守れ、値引きは却って気持ちを悪くするくらいが落ちだ
- 九、今日の損益を常に考えよ、今日の損益を明らかにしないでは、寝につかぬ習慣にせよ
- 十、商売には好況、不況はない、いずれにしても儲けねばならぬ
- まとめ
商売の心得「三方よし」で有名な近江商人とは?
江戸時代、近江の国(現在の滋賀県)から全国各地を行商して歩いた商人たちは「近江商人」と呼ばれていました。
その近江商人たちは次第に豪商として全国に名を轟かせていきました。
伊藤忠商事・高島屋・日本生命・西武グループ・ワコールなどは、近江商人をルーツにもつ企業だとか。
近江商人といえば「三方よし」という商売の心得えが有名です。
「三方よし」とは「売り手よし・買い手よし・世間よし」のことを言います。
これは
「売り手だけではなく、買い手心の底から満足し、また社会の発展に貢献できるのが良い商売である」
という意味です。
「三方よし」は商売人には広く知られている商売の鉄則ですが、実は他にも近江商人の商売の心得があるのです。
それが次にご紹介する近江商人の「商売の十教訓」というものです。
近江商人の経営哲学「商売の十教訓」とは?
一、商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり
商売とは世の為、人の為に奉仕をすることである。
世の為、人の為に商売を行えば、利益は後からついてくる。
二、店の大小よりも場所の良否、場所の良否よりも品の如何
店の大小は問題ではない。
商売をする場所が良い悪いという問題でもない。
良い商品をお客さんに提供できれば商売は繁盛する。
三、売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永遠の客をつくる
「商品を売りさばければそれで良い。後のことは知らない。」というのでは繁盛しない。
商品を売った後にいかにお客さんにサービスを提供できるのかが大切である。
そうすればそのお客さんはリピーターになってまた商品を買ってくれるし、評判を広めてくれる。
四、資金の少なきを憂うなかれ、信用の足らざるを憂うべし
資金の少ないことを嘆くことはない。
むしろお客さんへの信用が足りないことを嘆くべきである。
お客さんからの信用を得ることにまずは励むべきである。
五、無理に売るな、客の好むものも売るな、客の為になるものを売れ
商品を無理やり売りつけることはしてはいけない。
お客さんの「好むもの」を売るのも本当の商人ではない。
本当の商人とはお客さんの「為になるもの」を売るものである。
六、良きものを売るは善なり、良き品を広告して多く売ることはさらに善なり
良い商品を売ることは善の行いと言える。
良い商品を多くの人たちに買ってもらう努力を重ねることは、それだけ世の中の為になることであるから良い行いといえる。
七、紙一枚でも景品はお客を喜ばせる、つけてあげるもののないとき笑顔を景品にせよ
紙一枚のサービスでもお客さんは喜んでくれるものである。
商品を買ってくれたお客さんには、何でもいいのでサービス品を提供すべきである。
提供できるサービス品が何もなければ、あなたの笑顔を分け与えなさい。
八、正札を守れ、値引きは却って気持ちを悪くするくらいが落ちだ
「正直な値段」で一生懸命「正直な商売」をするのが商売繁盛のコツである。
不当な利益を得ようとすればお客さんは離れる。
しかし定価で売らず無理な値引きをするのは、いずれお客さんからの信頼が無くなるし、自らの商売が成り立たなくなるということを忘れてはいけない。
九、今日の損益を常に考えよ、今日の損益を明らかにしないでは、寝につかぬ習慣にせよ
常に損益のことを考え商売をするのが本当の商人である。
いい加減などんぶり勘定では末永く繁盛していくことはできない。
今日一日でどれだけの損益が出たかしっかり計算しないうちは夜寝てはいけない。
十、商売には好況、不況はない、いずれにしても儲けねばならぬ
「今は景気が悪いから物が売れない」というのは言い訳に過ぎない。
商売人とはどんなときでも色々な努力や工夫をして儲けを出していくものである。
まとめ
近江商人の「商売の十教訓」をご紹介しました。
有名な「三方よし」以外にも、近江商人には商売の鉄則というものがあるんですね。
「いかにお客さまのためや世の中のための商いを出来るか?」というのが経営の真髄なんですね。
「商売の十教訓」は近江商人の経営哲学が凝縮された、どの時代にも活用できる商売の鉄則だなと感じました。
今回はこれにて!
ささぶねでした!
ささぶねの詳しいプロフィールはこちら!⇒ プロフィールを見る
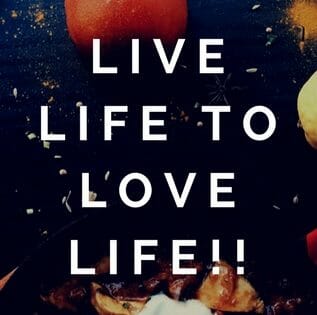

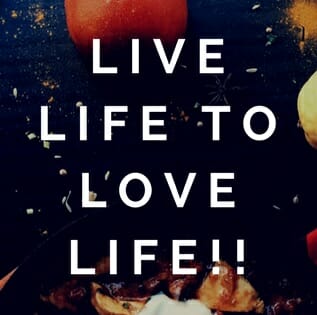
コメント